【朗報】フードパスポートがアップデート!月額料金と頻度の変更点のまとめと独自分析(2019年4月26日より)
.png)
スポンサードリンク
スポンサードリンク
どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)
フードシェアリング、フードパスポート(FOODPASSPORT)はご存知でしょうか?
「フードパスポート」とは、飲食店のおまかせメニューとユーザーをマッチングさせる月額定額制サービスになります。2019年4月26日より、フードパスポートのサービスが変更しました。この変更でフードパスポートがより活発になり、フードロスを削減できるのではないかと思います。
今回は、「フードパスポート」の利用における変更点のまとめ(2019年4月26日以降適用)とその効果と現状課題を独自分析してみたいと思います。2018年10月にリリースされ、順調に拡大しております。
フードロスに向き合う多種多様なサービスに関して、独自にまとめたページはになります。
「FOOD PASSORT」(フードパスポート)とは

まず、フードパスポート(FOODPASSPORT)とは、どんなサービスでしょうか?
「フードパスポート」とは、飲食店のおまかせメニューとユーザーをマッチングさせる月額定額制サービスになります。店舗とユーザーのマッチングによって飲食店で発生するフードロスの削減の意図しております。店内飲食が前提で、店によってはチャージ・つきだし等の提供がルールの場合もありますよ。
①実は、「フードパスポート」は余剰食品削減プラットフォームと予約サービスとのハイブリッドであるということ
②「Reduce Go」の関西版?「フードパスポート」とは?「Reduce Go」との9つの違いと5つの共通点をまとめてみた。
③「フードパスポート」は「TABETE」との9つの違いと4つの共通点をまとめてみた。【徹底分析】
④大阪のフードシェアリング、FOODPASSPORT(フードパスポート)のサービスの登録方法と利用方法【写真解説あり】
⑤「フードパスポート」を利用するうえで知っておきたい10の注意事項
【2020年3月18日追記】
フードパスポートは、関西圏(近畿2府4県)からサービス展開し、関東(1都3県)にも進出し、様々なフードシェアリングサービスの中で加盟店舗数No.1を誇るサービスにグロースしております。

*作成中
【追記】
様々なフードシェアリングサービスの中で加盟店舗数No.1を誇るサービスに拡大していましたが、新型コロナウィルスの影響に伴い、2020年4月30日をもってサービスを停止しています。
なお、今後の再開時期に関しては未定とのことで、サービスの再開を心待ちにしています。
「FOOD PASSORT」(フードパスポート)の変更点のまとめと変更に関する分析
2019年4月26日から適用される「フードパスポート」のサービス変更について要約してみました。
- 月額利用料金(税別)の変更 2,980円→980円に変更
- 利用回数の上限設定 上限なし→月10回までの利用可能
月額利用料金の変更とその予想効果
「フードパスポート」では、月額利用料金が変更になりました。
月額料金変更の狙いは、新規顧客の開拓とチャーンレート(解約率)の改善ではないかと思われます。
①月額料金を安くすることで、新規顧客のハードルを下げることができます。
②「フードパスポート」は、ブスクリプションモデルであるため、チャーンレート(解約率)を意識していることでしょう。そのチャーンレートが想定しているより高かったために、月額料金を下げてチャーンレートを下げるための施策ではないかと思いました。継続的に利用してもらえることが収益性のアップにも繋がりますので。
★分析に使用した本はこちら♪(初級編)
サブスクリプション・マーケティング――モノが売れない時代の顧客との関わり方
利用回数の上限設定とその予想効果
「フードパスポート」では、利用回数の上限が設定されました。1日1店舗までの利用に関しては変更になっておりません。1日は、AM0:00~PM24:00までを1日を定義しております。
毎日外食する層利用者が現実的にはほぼいないとのことが判明したのでしょうね。「フードパスポート」利用しているユーザーが毎日外食するとは思えませんでしたので、現実的な路線への変更になったでしょう。
外食に関するアンケート結果
マイボイスコム株式会社は、『外食』に関するインターネット調査を2018年10月1日~5日に実施し、10,521件の回答を集めたとのことでした。
●調査要約
■昼食や夕食に外食する人は9割弱。月1回以上外食者は昼食6割強、夕食5割強。昼食の外食頻度は男性で高い傾向
■外食する人の、1回あたりの支出額は、昼食は「800~1,000円未満」、夕食は「1,000~1,200円未満」がボリュームゾーン。昼食の支出額は2013年以降高価格帯の比率が増加傾向
『外食』に関するインターネット調査によると、毎日外食する頻度は2.3%(n=10521)であり、フードパスポートをグロースするためには、この層をターゲットにするにはあまりにも少ないと言えるでしょう。
フードパスポートの変更点から分析するFOOD PASSORTの現状の課題
フードパスポート(FOODPASSPORT)のサービス変更点を上記でまとめてみました。その変更点から独自析してみると、フードパスポートの現状の課題は、下記の項目ではないでしょうか?
フードパスポートが採用するサブスクリプション型モデル(継続課金モデル)では、マーケティングファネルが機能しません。
.001-1024x768.jpeg)
一度きりの販売の場合、マーケティングファネルに基づいて、新規顧客を見込み客へ、見込み客を顧客へ変えるモデルが必要でした。そのため、顧客になってから既存顧客に対する施策や方法は必要ありませんでした。
しかし、継続課金モデルでは、新規顧客を見込み客へ、見込み客を顧客になってからがスタートになります。つまり、既存顧客との価値の育成と信頼の維持に注力する必要があります。徹底的に利用者との会話によって、サービスを改善する必要があります。
もちろん、新規顧客の獲得も必要ですが、これまで以上に既存顧客のフォローが必要になります。既存顧客の維持と新規顧客の獲得のコストを考えると、圧倒的に既存顧客の維持がコストが安いため、既存顧客の維持に努める必要があり、このようなアップデートされたのだと思います。
★分析に使用した本はこちら♪(上級編)
最後に
今回は、「フードパスポート」の利用における変更点のまとめ(2019年4月26日以降適用)とその効果と現状課題について分析してみました。
新規顧客にとっても、既存顧客にとってもベストのアップデートではないでしょうか?
フードロス削減の大きなムーブメントをつくり上げていくために、フードパスポートはユーザーとともにサービスを発展させております。今後もさらなる飛躍を期待しております。
フードロスに向き合う多種多様なサービスに関して、独自にまとめたページはになります。
「食彩life」の運営者 dai が食品業界を分析した内容を無料で配布しております。
令和時代に向けて是非とも知っておきたい食品業界情報になりますよ。
食品業界の実態・トレンドを知ることで、食品業界の知識の向上に役立たせることができます。また、食品業界を目指している方にとって、食品メーカーで従事していた生の意見(一次情報)を知ることができます。
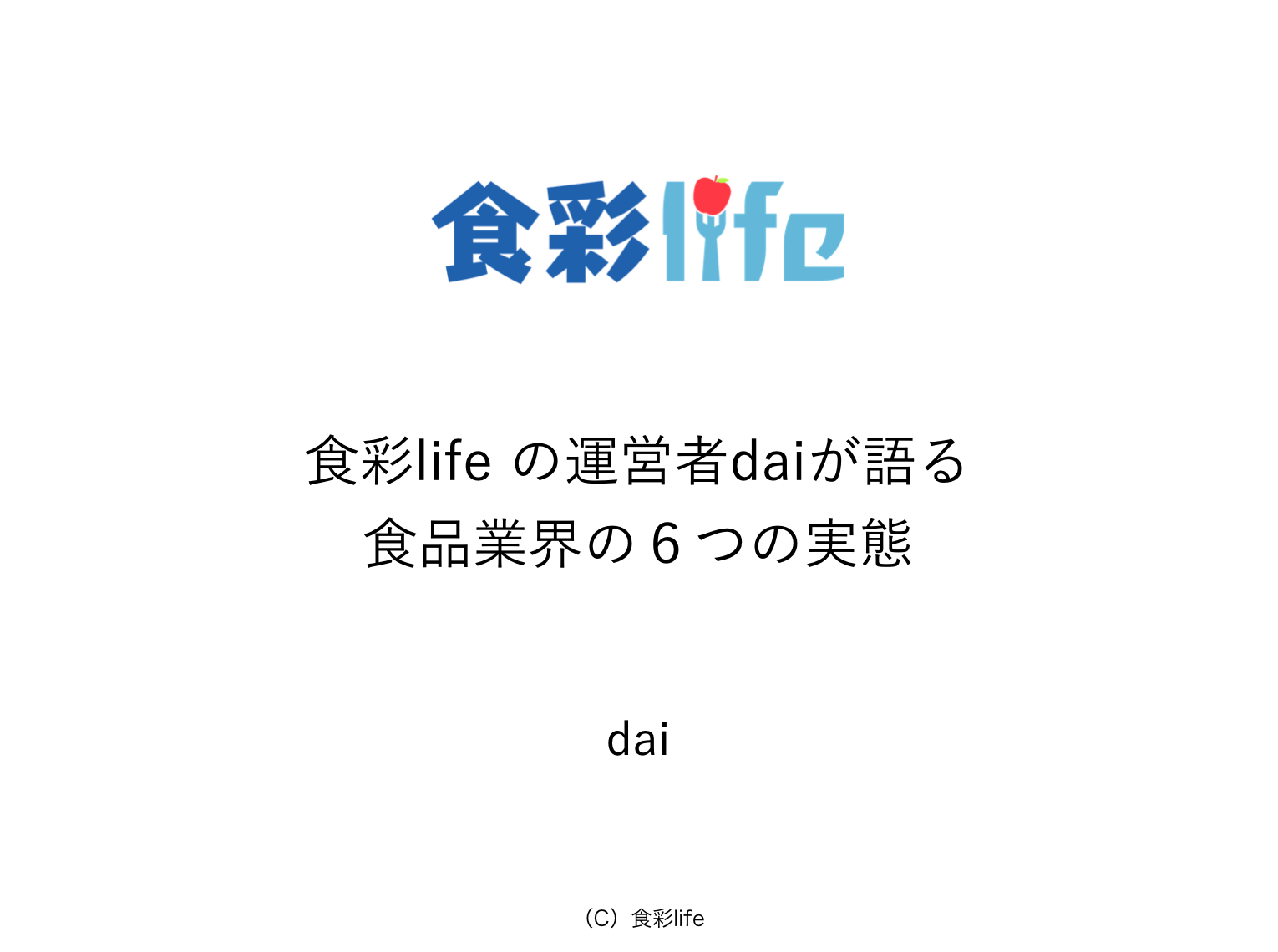
関連記事
最新記事
スポンサードリンク
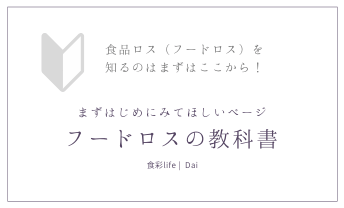

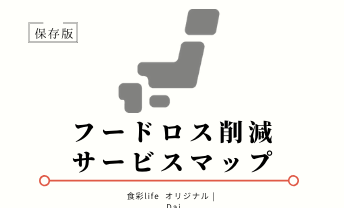





の登録方法とサービスの利用方法をまとめてみました。-175x117.png)

が届く?saketakuで届いた日本酒2本を分析・堪能してみた。【13回目利用】-175x117.png)

