クーポンなどのインセンティブによってフードロスを削減?消費者の意識改革を目指すサービス3選

スポンサードリンク
スポンサードリンク
どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)
2018年は様々なフードロス削減サービスがロンチされて、フードロス元年と謳える年ではないかと個人的には分析しております。2019年もフードロスに関して世間の関心が高まり、ますます活況を帯びております。
TABETE、ReduceGoなどのフードシェアリングは外食の余剰食品を解決するサービスになりますが、人間の本質的な価値観に向き合い、変換を促すサービスがあります。クーポン・ポイントなどのインセンティブによってフードロスを削減するサービスで、海外ではNo Food Wasted、Froodlyなどが挙げられます。
今回は、日本におけるインセンティブによるフードロス削減を目指すサービス3選についてまとめてみました。消費者の意識改革に向き合ったサービスであると言えます。
フードロスとは

本題に入る前にフードロス(食品ロス)について説明します。
フードロス(食品ロス)とは、食べるために作られた食料が、失われたり捨てられたりしてしまうことを指します。サプライチェーンの流れの中で、まだ食べられるにも関わらず、様々な理由で失われたり、捨てれられたりしています。フードロスの定義は様々ですが、このHPでは、フードロスを環境省や農林水産省が用いられているように「食べられる食べ物が捨てられること」という意味で使用しております。
2015年に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2016年から2030 年までの国際目標の中で、食品ロス関係の記載があり、持続可能な生産消費形態を確保する目標を掲げております。
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる、とのことでした。
日本のフードロスは年間643万トン。そのうち家庭から291万トンが発生
実際、日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまっている、フードロス量は、643万トンと推計されております。(2016年度)

まだ食べられるものが捨てられてしまう問題、フードロスについて、社会全体が考えていかなければならない課題になります。日本のフードロスのうち291万トンが、消費段階の家庭で発生していると言われており、一人一人が行動の見直しがフードロスを減らしていく上で必要になります。
さらに、フードロスに関して深く知りたい方はこちら。
①フードロス(食品ロス)とは?食料ロスと食料廃棄の違いや原因など、食品従事者が徹底的にまとめてみた。
②今から家庭でできる!いち消費者の6つのフードロス対策【食品関係者記載】
③食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策とは【現役食品メーカー勤務者が分析】
インセンティブによるフードロス削減を目指すサービス3選
インセンティブによるフードロス削減を目指すサービス3選をまとめてみました。そもそもインセンティブとはどのような行為を指すのでしょうか?
インセンティブとは、行動するための刺激となるもので、例えば、決算セールやポイント還元セールなどがさしたる例でお店側は購入してもらうためにインセンティブを用意しております。フードロスを削減するために、インセンティブによって消費者意識を喚起し、行動を促すサービスをまとめてみました。
- ドコモが実証実験 「EcoBuy」
- 完食割合によってポイントがつく 「Can食」
- 静岡市が主導 「ふじのくに食べきりやったね!キャンペーン」
ドコモが実証実験 「EcoBuy」
として、-NTTドコモが実証実験.png)
東京都では、持続可能な資源利用に向けたモデル事業を企業などと連携して実施しております。
その一つとして、NTTドコモが実証実験、EcoBuyがあります。EcoBuyとは、スマートフォンアプリを活用して賞味期限が迫った食品を購入した消費者にポイントを付与することによって、食品ロスを減らす仕組みを構築するサービスになります。
- 実施期間:2018年1月19日〜2月28日
- 店舗:mini ピアゴ入船一丁目店(東京都)
- 実験内容:スマートフォンアプリを活用して賞味期限が迫った食品を購入した消費者にポイント(dポイントなど)を与えることで、食品ロス削減に有効かどうか確認。
実験データの数値に関して公表されていないので確認しようがありませんが、最近、ローソン1やセブン-イレブン・ジャパン2がポイント還元による食品ロス削減を実施するとのことでした。そのため、全く効果がなかったとは考えにくいです。
1:ローソンが顧客と一緒に取り組む食品ロス削減プログラム「Another Choice(アナザーチョイス)」をモニタリングするとのこと。(2019年6月11日〜8月31日に愛媛県と沖縄県で実証実験)
2:2019年秋ごろから、セブン-イレブン・ジャパンでもnanacoポイント還元を行うとのこと。
完食割合によってポイントがつく 「Can食」

(画像引用:目指せ、食べ残しゼロ。起業して、完食が評価されるサービスを。(井下田 淳 2019/01/23 公開) – クラウドファンディング Readyfor (レディーフォー) )
「Can食」(完食-ポン)とは、飲食店で食事を完食した写真を投稿することで、クーポンなどがもらえるポイントを貯められるサービスになります。2019年6月にリリース予定になります。
飲食店利用時に食べ終えた皿の写真をアプリ内で送信することでポイントがたまり、そのポイントがその店舗のクーポンやサービス、商品などに代えることができるようになります。
完食することで消費者にポイントがつき、食べ残しゼロの社会を目指されているとのことでした。完食割合によってもポイントがつくとのことでした。
アプリに必要なハマる仕掛けに基づいた設計をされており、プロダクトを習慣化させ食べ残しゼロの世界を作るために、必要なトリガー(きっかけ)、アクション(行動)、リワード(報酬)が備わっているように感じました。詳しくはこちらでまとめております。
静岡市が主導 「ふじのくに食べきりやったね!キャンペーン」

「ふじのくに食べきりやったね!キャンペーン」とは、静岡県が行う食品ロス削減に向けた県民参加型のキャンペーンになります。食べきり協力店で料理を残さず食べると無料アプリ「クルポ」によりポイント付与されます。ポイントを集めると、抽選に応募できます。
- 実施期間:2018年6月5日〜2019年3月31日
- 目的:県民一人ひとりに楽しみながら温暖化防止活動を実施してもらうこと
- 使用方法:無料アプリ「クルポ」を活用し、食べきることでポイントが獲得できます。
静岡県では2020年までに一般廃棄物排出量を1人1日当たり815g以下にすることを目標としており、廃棄物の削減の目的として「ふじのくに食べきりやったね!キャンペーン」を実施されておりました。
まとめ
上記のインセンティブによるフードロス削減を目指すサービスを要約してみました。
| サービス | 概要 |
| ①EcoBuy | NTTドコモの実証実験で
賞味期限が迫った食品を購入した消費者に
ポイントを付与することによって、
食品ロスを減らす仕組みを構築。 |
| ②Can食 | 完食割合によって
ポイントがもらえ、クーポンが使える。 |
| ③ふじのくに食べきりやったね!
キャンペーン |
静岡県が行う
食品ロス削減に向けた
キャンペーンで食べきることで
ポイントがもらえる。 |
さらに詳しくご覧になりたい方はこちらへ。様々な観点でフードロスに関してまとめております。
最後に
今回は、インセンティブによるフードロス削減を目指すサービス3選についてまとめてみました。
食品業界で働く同業者として様々なサービスを研究しております。自分に合うサービスがあり機会があればご利用いただくのもアリかと思います。
フードロスに向き合う様々なサービスに関して、独自にまとめたページはこちらになります。ご関心があれば是非どうぞ^^
「食彩life」の運営者 dai が食品業界を分析した内容を無料で配布しております。
令和時代に向けて是非とも知っておきたい食品業界情報になりますよ。
食品業界の実態・トレンドを知ることで、食品業界の知識の向上に役立たせることができます。また、食品業界を目指している方にとって、食品メーカーで従事していた生の意見(一次情報)を知ることができます。
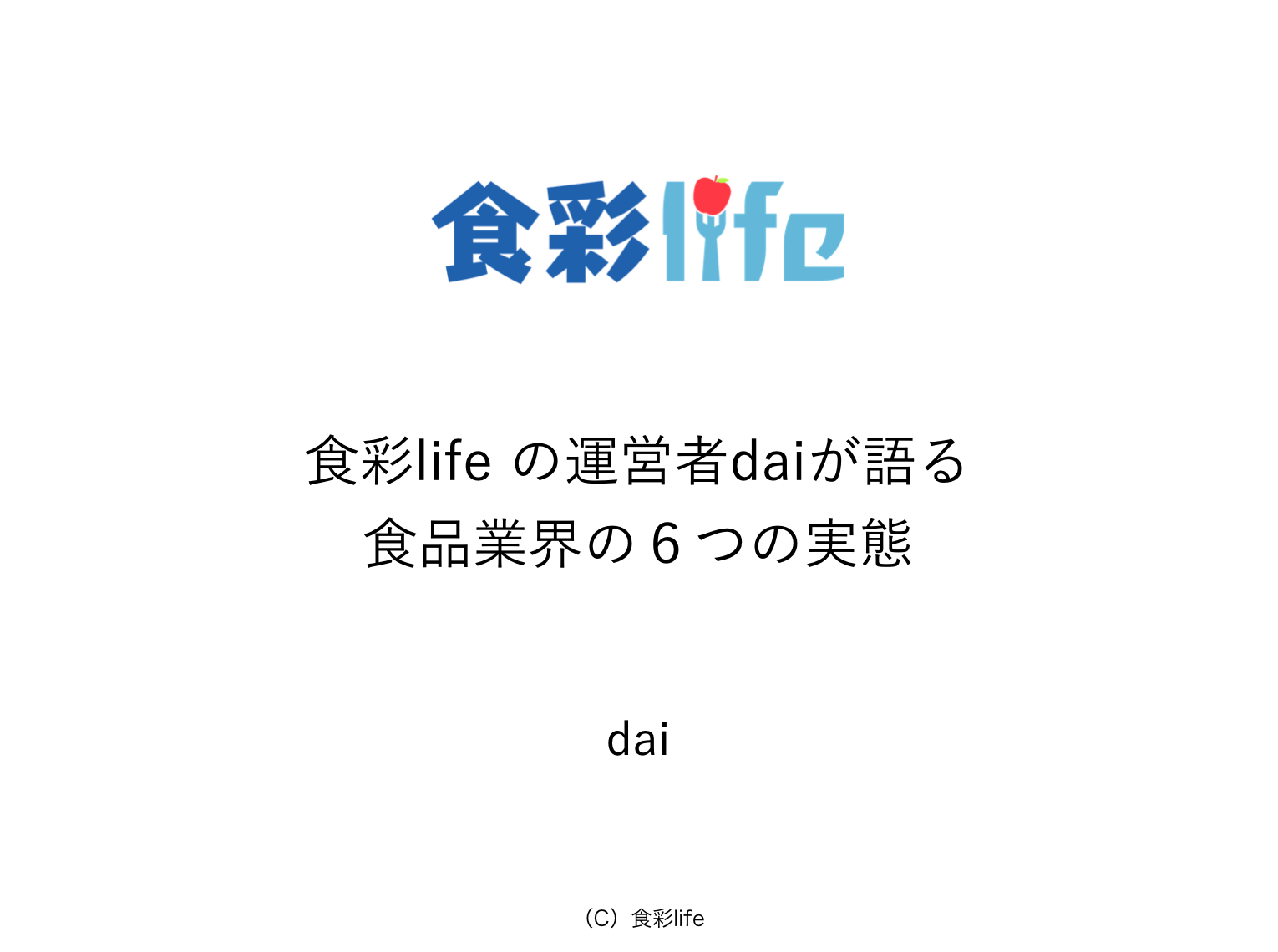
関連記事
最新記事
スポンサードリンク
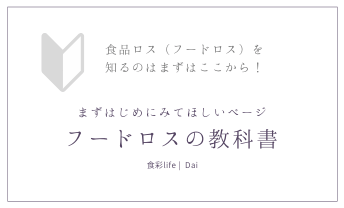

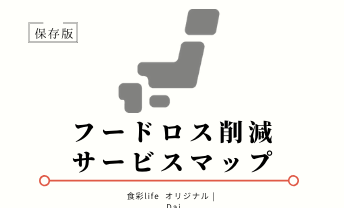
を使用する上で知っておきたい9の注意事項-175x117.png)
の4つの魅力的なポイント-175x117.png)
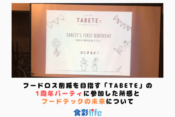


が届く?saketakuで届いた日本酒2本を分析・堪能してみた。【13回目利用】-175x117.png)

