食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策とは【食品従事者が分析】
スポンサードリンク
スポンサードリンク
どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)
フードロスに対して消費者ができることを前回まとめてみました。フードロスは生産、流通、販売、消費といったサプライチェーンのすべての段階で原因が潜んでおり原因を特定化できず、幅広い対応が求めれらております。
では、食品業界としてフードロスに対して貢献できることは何があるでしょうか。今回は、食品業界が取り組むべきフードロス対策について食品従事者のdaiが分析してみたいと思います。
フードロスとは

フードロス(食品ロス)とは、食べるために作られた食料が、失われたり捨てられたりしてしまうことを指します。サプライチェーンの流れの中で、まだ食べられるにも関わらず、様々な理由で失われたり、捨てれられたりしています。フードロスの定義は様々ですが、このHPでは、フードロスを環境省や農林水産省が用いられているように「食べられる食べ物が捨てられること」という意味で使用しております。
2015年に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2016年から2030 年までの国際目標の中で、食品ロス関係の記載があり、持続可能な生産消費形態を確保する目標を掲げております。
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる、とのことでした。
●フードロス(食品ロス)の教科書を作ってみた。【基礎知識を楽しく学ぶ7章】 →フードロスを勉強する上で教科書を作ってみました。よかったら参考にしてください。
日本のフードロスは年間643万トン。そのうち家庭から291万トンが発生
実際、日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまっている、フードロス量は、643万トンと推計されております。(2016年度)

まだ食べられるものが捨てられてしまう問題、フードロスについて、社会全体が考えていかなければならない課題になります。日本のフードロスのうち291万トンが、消費段階の家庭で発生していると言われており、一人一人が行動の見直しがフードロスを減らしていく上で必要になります。
さらに、フードロスに関して深く知りたい方はこちら。
①フードロス(食品ロス)とは?食料ロスと食料廃棄の違いや原因など、食品従事者が徹底的にまとめてみた。
②今から家庭でできる!いち消費者の6つのフードロス対策【食品関係者記載】
③食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策とは【現役食品メーカー勤務者が分析】
食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策
フードロスに関して、流通段階で様々な原因が潜んでおり、一つの原因に特定できず、幅広い対策が求められております。当事者意識を持ちにくい。ただ、先送りにしてよい問題ではありません。食品業界全体が、取り組んでいく必要があります。業界全体として取り組むべき対策を関係者としてまとめてみました。
- AI、IoTを利用した需要予測を高める(過剰生産をなくす、気象データを反映)
- 「3分の1ルール」の緩和
- 賞味期限の年月表示の移行
- 惣菜、中食部門の食品ロス削減(店舗ロス率が非常に高い)
- チルド食品、日配食品の賞味期限の延長
- 小売現場での売り切る意識の向上
- 廃棄物を活用した加工品への応用(柿の皮を利用した市田柿コスメ/(株)マツザワ)
- ダイナミックプラシング(消費期限に応じた自動価格表示)の導入
AI、IoTを利用した需要予測を高める
フードロスの原因の一つに誤った需要予測があります。販売できると想定したものの、実際は売れず売れ残ってしまう実態があります。そのような過剰生産をなくす必要があります。特に、季節商材やイベント商材は顕著です。
あらゆるITを活用して需要予測を高め、過剰生産をなくすことがフードロスにつながります。実際、気象データに基づいた需要予測の導入しているメーカーもあります。森永製菓の場合、「チョコモナカジャンボ」の生産調整での気象変化に基づいた生産調整を考え、利益を確保しているとのことでした。
参考:2017年9月5日放送「ガイアの夜明け/異変の夏…〝激闘″シェア争い!」
「3分の1ルール」の緩和
食品業界には、「1/3ルール」という慣習があります。このルールがフードロスを助長していると思われます。「1/3ルール」とは、製造日から賞味期限までを3分割した上で、納品期限、販売期限を設けるという小売有利なルールになります。
販売期限を超えた食品は小売から卸売へ、納品期限を超えた食品は小売および卸売からメーカーへと返品され、その多くが廃棄されているとのことでした。
もちろん「1/3ルール」がある小売店もあありますが、期限を設けていない店の方が多いです。むしろ処分品を求める小売店が多くあります。その上、「1/3ルール」をすぎて返品されたとしても、メーカー側で廃棄することは基本的にはあり得ません。処分販売や価格が見えない先(業務用ルート)で販売処理しますね。
ただ、まだこのようなルールがあるのも実情のため、緩和していく必要があります。
賞味期限の年月表示の移行
賞味期限の表示を年月日表示から年月表示の移行が望ましいと思っております。
賞味期限の年月日表示の場合、荷受けの管理が日付単位で行わないといけません。万が一、ロットが逆転して郵送してしまえば原則荷受け不可のため、その商品は返品になります。自社のNB商品であれば転売することができますが、委託先のPB商品の場合、転売することもできず、廃棄になります。
そのため、月単位の管理の方が納品先がスムーズ受け入れ可能になり、物流として確認作業をショットカットでき、波及効果が大きい取り組みになります。
関連記事:【PB商品の商品化実績あり】NB商品とPB商品の違いと実態を食品メーカーの営業マンがまとめてみた。
惣菜、中食部門の食品ロス削減
惣菜、中食部門の食品ロス削減は目下の課題になります。店舗でのロスが非常に高く、いかにしてロスを減らしていくかが考えていく必要があります。中食といえば、百貨店のデパ地下が有名ですが、ディスプレイにいっぱいの商品が陳列されております。フードロスも致し方ないといった売り方になります。
百貨店側の意向もありなかなか売り切れごめんの販売モデルがしづらいですが、売り切るモデルの構築を今後業界全体として考えていく必要があります。
チルド食品、日配食品の賞味期限の延長
チルド食品や日配食品の賞味期限の延長を各社取り組むことが結果としてフードロス対策になります。包材のディフェンス性、製法の開発など賞味期限の延長が可能であれば、積極的に取り組むべきだと考えます。
小売現場での売り切る意識の向上
小売の現場で各従業員がそれぞれ売りきる意識の向上を持って従事することが大事です。余れば廃棄すれば良いのではなく、惣菜や賞味期限が短い商品は見切り価格を出してでも、販売することが大事です。見切り価格をなるべく出したくないのであれば、販売する量の惣菜を調整しておこう。
廃棄物を活用した加工品への応用
廃棄物を活用した加工品への応用・販売によって、廃棄するのではなく、販売することができます。例えば、株式会社マツザワが製造した柿の皮を利用した市田柿コスメがあります。

柿の皮を一般廃棄物としてコストをかけ焼却処分されておりましたが、 農業残渣である市田柿の皮を原料として使用する事により、フードロスの解決の一助になりえますね。
ダイナミックプラシング(消費期限に応じた自動価格表示)の導入
ダイナミックプライシング(消費表示に応じた自動価格表示)の導入がフードロス削減につながります。
需給状況に応じて価格を変動させることによって需要の調整を図る手法。需要が集中する季節・時間帯は価格を割高にして需要を抑制し、需要が減少する季節・時間帯は割安にして需要を喚起する。航空運賃・宿泊料金・有料道路料金などで導入されているほか、電力料金についても導入に向けて社会実験が行われている。
引用:ダイナミックプライシングとは – コトバンク
ダイナミックプライシングは、日本のプロ野球でも楽天などが導入しており、需給バランスによって価格を変動しております。それを食品業界でも導入することが重要です。
例えば、牛乳の購入する際に、後ろから購入する方もいらっしゃるかと思います。同じ価格であれば、後ろから賞味期限が長い商品を購入するのも想像つきますし、僕も購入したことがあります。でも、ダイナミックプライシングを導入すれば賞味期限の差によって価格を変動させることができます。
そのようにすれば、無目的に何気なく後ろから牛乳を購入していた行為を考え直させ、状況に応じて購入してもらうきっかけになります。
最後に
今回は、食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策についてまとめてみました。
フードロスに関して様々な原因が潜んでおり、原因を特定することができず、様々な事柄に対して優先順位をつけながら対応する必要があります。食品業界が一つになって、フードロスの削減に対して取り組むべきだと思います。
フードロスに向き合う様々なサービスに関して、独自にまとめたページはこちらになります。ご関心があれば是非どうぞ^^
「食彩life」の運営者 dai が食品業界を分析した内容を無料で配布しております。
令和時代に向けて是非とも知っておきたい食品業界情報になりますよ。
食品業界の実態・トレンドを知ることで、食品業界の知識の向上に役立たせることができます。また、食品業界を目指している方にとって、食品メーカーで従事していた生の意見(一次情報)を知ることができます。
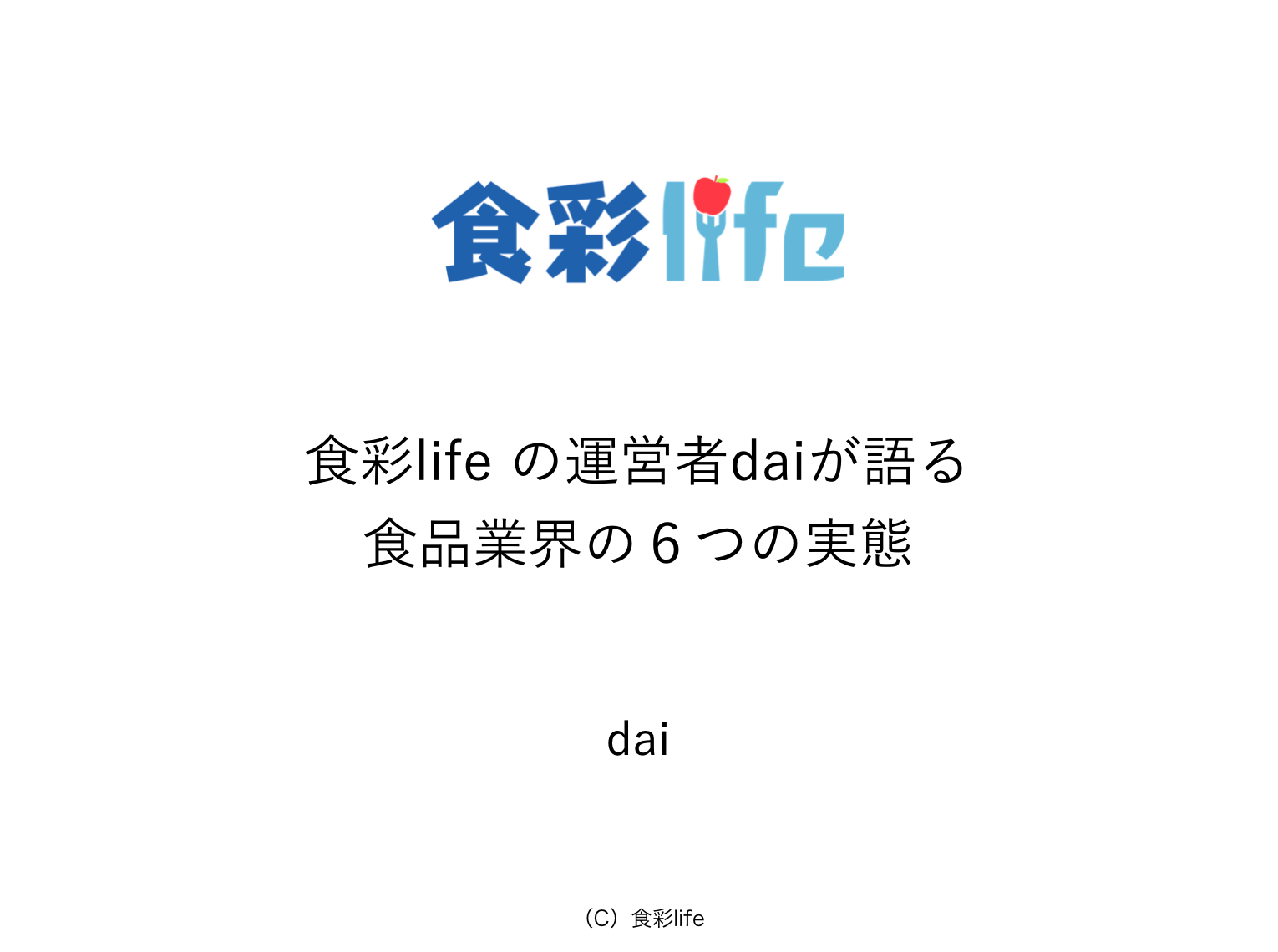
関連記事
最新記事
スポンサードリンク
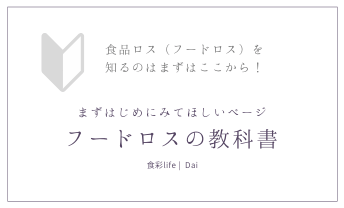

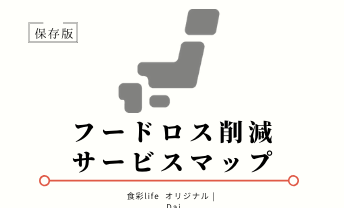
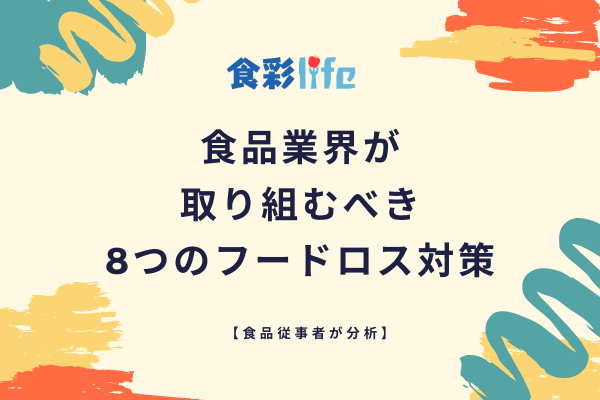
のサービスの登録方法と利用方法【写真解説あり】-175x117.png)

でまとめてみた。-175x117.png)


が届く?saketakuで届いた日本酒2本を分析・堪能してみた。【13回目利用】-175x117.png)

