今から家庭でできる!いち消費者の6つのフードロス対策【食品関係者記載】
スポンサードリンク
スポンサードリンク
どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)
フードロスに関して前回まとめてみました。フードロスは生産、流通、販売、消費といったサプライチェーンのすべての段階で原因が潜んでおり原因を特定化できず、幅広い対応が求めれらております。
では、僕たち消費者がフードロスに対して貢献できることは何があるでしょうか。今回は、消費者が今からでもできるフードロス対策について食品従事者がまとめてみたいと思います。
フードロスとは

フードロス(食品ロス)とは、食べるために作られた食料が、失われたり捨てられたりしてしまうことを指します。サプライチェーンの流れの中で、まだ食べられるにも関わらず、様々な理由で失われたり、捨てれられたりしています。フードロスの定義は様々ですが、このHPでは、フードロスを環境省や農林水産省が用いられているように「食べられる食べ物が捨てられること」という意味で使用しております。
2015年に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2016年から2030 年までの国際目標の中で、食品ロス関係の記載があり、持続可能な生産消費形態を確保する目標を掲げております。
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる、とのことでした。
●フードロス(食品ロス)の教科書を作ってみた。【基礎知識を楽しく学ぶ7章】 →フードロスを勉強する上で教科書を作ってみました。よかったら参考にしてください。
日本のフードロスは年間643万トン。そのうち家庭から291万トンが発生
実際、日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまっている、フードロス量は、643万トンと推計されております。(2016年度)

まだ食べられるものが捨てられてしまう問題、フードロスについて、社会全体が考えていかなければならない課題になります。日本のフードロスのうち291万トンが、消費段階の家庭で発生していると言われており、一人一人が行動の見直しがフードロスを減らしていく上で必要になります。
さらに、フードロスに関して深く知りたい方はこちら。
①フードロス(食品ロス)とは?食料ロスと食料廃棄の違いや原因など、食品従事者が徹底的にまとめてみた。
②今から家庭でできる!いち消費者の6つのフードロス対策【食品関係者記載】
③食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策とは【現役食品メーカー勤務者が分析】
僕たち消費者が今からでもできる、6つのフードロス対策
フードロスに関して様々な原因が潜んでおり、当事者意識を持ちにくい。ただ、先送りにしてよい問題ではありません。今生きている私たちがしっかりと向き合う必要があります。今からでもできるフードロス対策をまとめてみました。
- 賞味期限を切らさずに食べる。
- 食べきれる量を購入する。
- 外食で食べ残しをしない。
- 状況に応じて、手前の牛乳から購入する(日付の新しいものから取らない)
- 規格外品の知識を持つ
- 消味期限の正しい定義を知る(ただしメーカーの保証は賞味期限内)
賞味期限を切らさずに食べる。
賞味期限を切らさずに食べきることが重要であります。やはり、賞味期限が切れてしまうと、捨ててしまいます。賞味期限を切れる前に食べてしまいましょう。
食べきれる量を購入する。
賞味期限を切らさずに食べるきるためには、食べ切れる量を購入することをお勧めします。スーパーマーケットやコンビニエンスストアに行けば、様々な商品が陳列されており、購入意欲を煽ります。しかし、ご家庭で食べ切れる量を意識して、購入することが余計なフードロス を出さない上で大事です。
また、以前食べ切れず賞味期限を切れてしまった食材、調味料に関しては、量を調整して購入しよう。例えば、僕は妻と二人で生活しておりますが、酢を頻繁には使わないため、小さめのサイズに入った酢を購入しております。
量が多いからお得、特売してるからサイズの大きいものではなく、そもそも使い切れる量なのかを検討することが肝要です。もちろん、大きいサイズの食材を購入して、調理できるように毎日の食事を調整できるのであれば問題ありませんが…
外食で食べ残しをしない。
当たり前のことですが、外食で食べ残ししないことを意識しよう。特にバイキングなど、取りすぎに注意が必要です。自分のお腹と相談して取りましょう。「もったいない」の意識を持つことが重要ですね。
状況に応じて、手前の牛乳から購入する(日付の新しいものから取らない)
こちらはどうしても強制することはできませんが、数日間で消費するのであれば、なるべく手前の牛乳から購入するようにしよう。
ただ、こちらはご家庭の状況によるかと思います。牛乳を飲む頻度が少なく、1週間以上消費にかかるであれば、長いにこしたことはありません。一方、お子様が多く牛乳を数日で消費するのであれば、前からとっても変わりありません。
無目的に後ろから牛乳を取ることはやめましょう。どうしても、同じ価格であれば賞味期限を長い商品を購入しがちであるのは重々分かりますが、少し考えてみましょう。
近い将来ダイナミックプライシング(消費期限に応じた自動価格表示)を小売で導入されるはずなので、その問題は解消されていくのでは、と個人的に推測しております。
規格外品の知識を持つ
日本では原則、規格に準拠した農産物が商品として扱われ一般流通します。規格に合致しない商品は中身は問題ないのにも関わらず、適正価格で販売することができません。日本では、規格品や見栄えの良い食品に関する信仰が強いように感じます。
規格外品、見た目が悪いだけの食品も問題ないのです。規格外品、少し見た目が悪くなった商品があっても食べられます。そのような知識を持って欲しいと願っております。
消味期限の正しい定義を知る(ただしメーカーの保証は賞味期限内)
消味期限の正しい定義を知ることが重要です。意外と知らない方が多いと思われます。
賞味期限とは
賞味期限とは、定められた方法により保存した場合、期待される品質が十分に保持される期限を示す年月日です。この年月日は製造者が理化学試験、微生物試験、官能検査などを行い、安全係数(1未満の係数)を勘案し短めに設定しているので、賞味期限がすぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。
- 表示対象:痛みにくい食品
- 食品の例:スナック菓子、カップ麺、缶詰、卵、牛乳、レトルト食品、冷凍食品など
つまり、賞味期限が切れていても食べることは正直可能で、1日程度なら僕は食べますね。ただ、乳製品関係は匂いがおかしければ食べませんが、切れていても食べることは可能になります。(ただし、おいしさの保証はありません。)
食品メーカーとしては、賞味期限の切れた商品に関しては食べないでくださいと案内するのが一般的です。賞味期限を切れた商品に関しては、(虐待検査などで、分析しているため食べることは可能ではあるものの)万が一を見越して食べないことを推奨されております。
<参考>消費期限とは
消費期限とは、定められた方法により保存した場合、腐敗や変敗のなどの品質の劣化による安全面での問題がないと認められる期限を示す年月日です。
- 表示対象:痛みやすい食品
- 食品の例:食肉、生カキ、弁当、サンドイッチ、生めん、生菓子など
最後に
今回は、消費者が今からでもできるフードロス対策についてまとめてみました。
フードロスに関して様々な原因が潜んでおり、当事者意識を持ちにくいですが、個々の人間がしっかりと向き合う必要があります。少しでもフードロスの削減を意識してみよう。小さな一歩が積み重なって、世界は良くなっていくと信じております。できることから一歩ずつ!!
フードロスに向き合う様々なサービスに関して、独自にまとめたページはこちらになります。ご関心があれば是非どうぞ^^
「食彩life」の運営者 dai が食品業界を分析した内容を無料で配布しております。
令和時代に向けて是非とも知っておきたい食品業界情報になりますよ。
食品業界の実態・トレンドを知ることで、食品業界の知識の向上に役立たせることができます。また、食品業界を目指している方にとって、食品メーカーで従事していた生の意見(一次情報)を知ることができます。
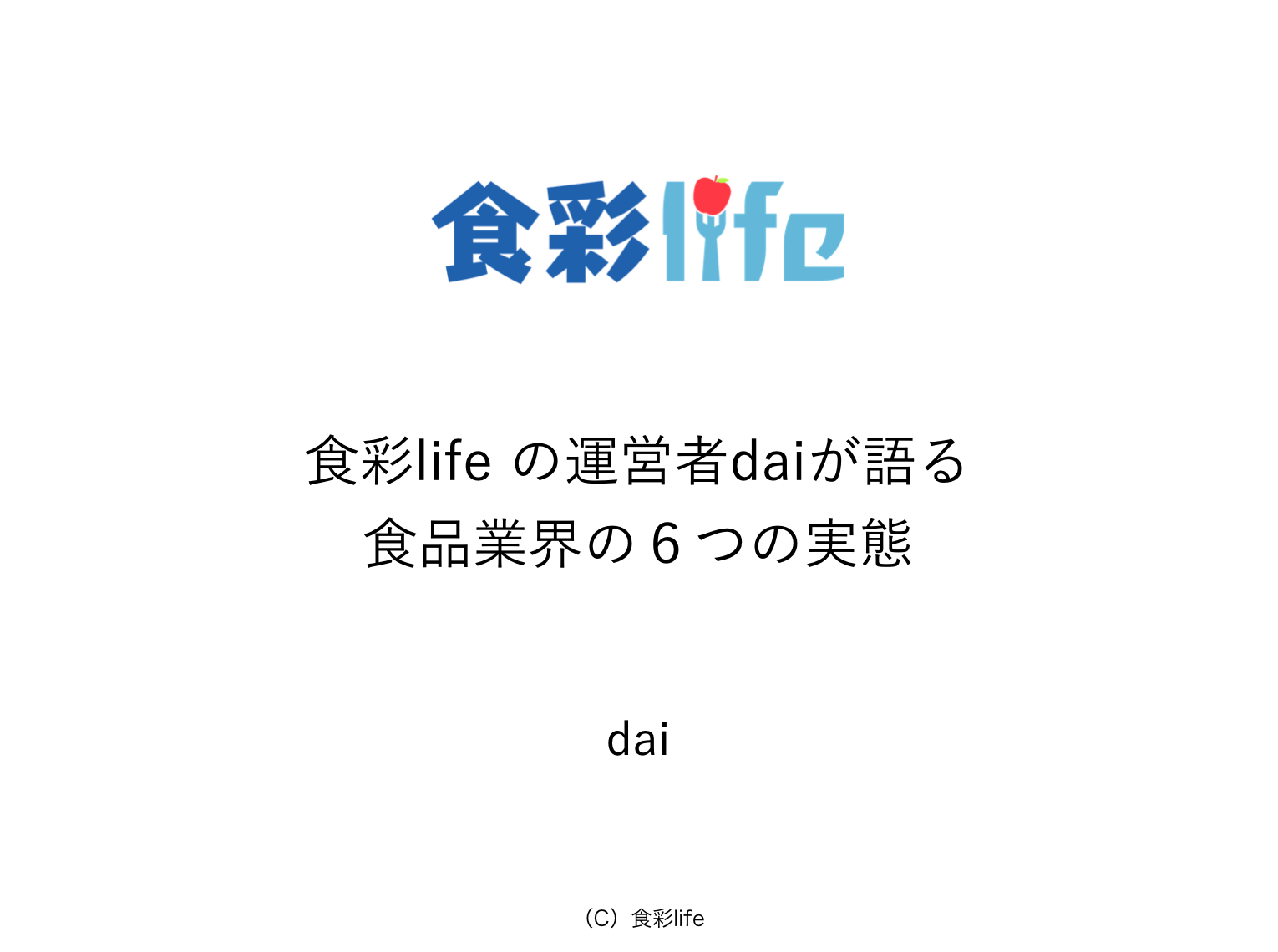
関連記事
最新記事
スポンサードリンク
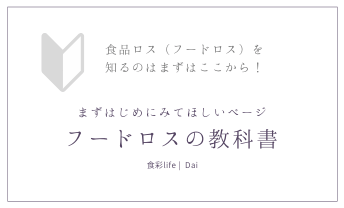

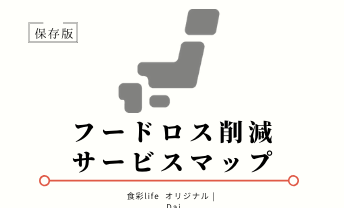


の登録方法とサービスの利用方法をまとめてみました。-175x117.png)



が届く?saketakuで届いた日本酒2本を分析・堪能してみた。【13回目利用】-175x117.png)


Comment
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]