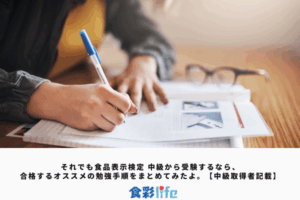どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)
惣菜管理士試験が2019年度10月開講分よりリニューアルされ、惣菜管理士3級のカリキュラムが変更しました。
今回は、リニューアルされた惣菜管理士3級の科目「栄養と成分」で最低限知っておきたい7のことについて記載したいと思います。ちなみに僕自身は惣菜管理士1級の資格を持っております。
惣菜管理士3級の難易度もそこまで難しくないため、それなりに勉強すれば受かりますよ。(得意先の人は一夜漬けで合格した方もいらしましたね)


まず、惣菜管理士3級について記載します。
<現在>惣菜管理士三級の試験範囲
2019年度10月開講分より、惣菜管理士3級のカリキュラムが変更になりました。
<以前>惣菜管理士三級の試験範囲
以前の惣菜管理士三級の試験範囲は下記の通りでした。参考程度に前回の科目も押さえておきましょう。
試験コンセプト:安全と栄養
レベル:基礎的な知識、担当者レベル
個人的に受講に当たっての感想(2015年)
該当年の試験に関して記載いたします。基本的に、「惣菜管理士問題集」のみ行えば合格可能になりました。ただし、設問の聞き方など丸暗記では対応できない工夫がしてあり、それなりに勉強することをお勧めします。周りに人は一夜漬けで合格した人もいました。僕自身は勉強しすぎたと思います。
- 勉強開始時期:試験2週間前から
- 平日の通勤時間:30分×2回
- テスト前週の土日:各1時間
- テスト前日:1時間
2018年惣菜管理士資格試験合格者および合格率
2018年惣菜管理士資格試験合格者及び合格率は、下記の通りになります。
| 級別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 一級 | 739名 | 606名 | 82.0% |
| 二級 | 1,032名 | 910名 | 88.2% |
| 三級 | 1,992名 | 1,616名 | 81.1% |
| 合計 | 3,763名 | 3,132名 | 83.2% |
「惣菜産業新聞JMニュース 2018.8.1発行」引用
ここから各単元ごとに暗記項目を記載しておきます。ここから各単元ごとに暗記項目を記載しておきます。
「栄養と成分」で最低限覚えておきたい7つのこと
「栄養と成分」で最低限覚えておきたい7つのことは下記の通りになります。
基礎代謝について
基礎代謝とは、呼吸、循環、排泄などの生理状態を維持するのに必要最低限のエネルギーのことをいいます。その上、基礎代謝は体重や体格、性別などの違いに影響され、体重と基礎代謝はかなり高い相関を示します。基礎代謝量は、成人男性が1,200〜1,600kcal、成人女性が1,000〜1,200kcalになります。
炭水化物について
炭水化物とは、エネルギー源としてもっとも摂取量が多い栄養素で、ヒトの体内で合成できず、食事で摂取するしかありません。糖類の結合の仕方により分類によって、単糖類、少糖類、多糖類に分類されます。
| 糖類 | 例 |
| 単糖類 | ブドウ糖(グルコース)、 果糖(フルクトース) |
| 二糖類 | ショ糖(スクロース)、 乳糖(ラクトース) |
| 少糖類 | マルトオリゴ糖 |
| 多糖類 | デンプン、セルロース |
また、炭水化物は、ヒトの消化酵素で分解されエネルギー源となる糖質と、ヒトの消化酵素で分解されずエネルギー源にならない、食物繊維に分類されます。
タンパク質について
タンパク質とは、アミノ酸が多数結合した高分子化合物です。アミノ酸同士の結合を、ペプチド結合と言います。また、タンパク質を分解する消化酵素は、ペプシン、トリプシン、キモトリプシンです。一般的に、アミノ酸価は、植物性タンパク質より動物性タンパク質のほうが栄養価が高くなります。(下の表を参照)
| 食品 | アミノ酸価 |
| 鶏卵 | 100 |
| 牛乳 | 100 |
| 精白米 | 61 |
| 小麦粉 | 31 |
9種類の必須アミノ酸について
アミノ酸が結合したものをタンパク質といいます。人間の身体を構成するアミノ酸は20s種類あります。そのなかで、体の中で合成されず、食物で摂取しなければならない必須アミノ酸は9種類あります。全て暗記しておこう。
- フェニルアラニン
- トリプトファン
- イソロイシン
- ロイシン
- バリン
- リジン
- スレオニン(トレオニン)
- ヒスチジン
- メチオニン
脂質・脂肪酸について
脂質とは、脂肪酸とグリセロールが結合した高分子化合物で、バター、マーガリンのような食用油脂や肉類などに多く含まれています。また、脂肪酸には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分類されます。
- 飽和脂肪酸:二重結合を持たない構造式。
- 不飽和脂肪酸:二重結合を一つ以上持つ構造式。
n-6系高不飽和脂肪酸とn-3系高不飽和脂肪酸の摂取バランスが重要と言われています。
- n-6系高不飽和脂肪酸:植物油(リノール酸)、肉類(アラキドン酸)に含まれます。
- n-3系高不飽和脂肪酸:魚介類に含まれる。秋刀魚、イワシ、サバなどに含まれます。
ビタミンについて
ビタミンとは、生体の機能を調節するために必要な栄養素で、体内では合成されないため、食べ物から摂取死泣けければなりません。主な生理作用をまとめてみました。
| ビタミン | 生理作用 |
| ビタミンA | 明暗調節、皮膚・粘膜などの上皮維持 など |
| ビタミンD | カルシウム・リンの吸収促進 など |
| ビタミンE | 抗酸化作用 など |
| ビタミンK | 血液凝固に関与、骨の形成に関与 など |
| ビタミンC | 抗酸化作用、コラーゲンの生成に関与 など |
亜鉛の過剰症と欠乏症について
亜鉛には、通常の食事で過剰症の事例は見られていないが、サプリメントによる亜鉛の過剰摂取は、銅の吸収阻害を引き起こすため、貧血につながることもあります。また、亜鉛の摂取が足りなくなると、味覚障害、嗅覚障害、発育低下が見られます。
最後に
今回は、リニューアルされた惣菜管理士3級の科目「栄養と成分」で最低限知っておきたい7のことについてまとめてみました。
惣菜管理士三級を受験される方にとって、参考になれば幸いです。業務をしながらの受験になるかと思いますが、効率的に勉強しましょう。