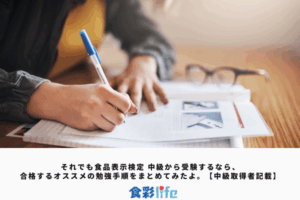どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)
惣菜管理士試験が2019年度10月開講分よりリニューアルされ、惣菜管理士3級のカリキュラムが変更しました。
今回は、リニューアルされた惣菜管理士3級の科目「食品の特性と惣菜」で最低限知っておきたい7のことについて記載したいと思います。ちなみに僕自身は惣菜管理士1級の資格を持っております。
惣菜管理士3級の難易度もそこまで難しくないため、それなりに勉強すれば受かりますよ。(得意先の人は一夜漬けで合格した方もいらしましたね)

惣菜管理士3級について

まず、惣菜管理士3級について記載します。
<現在>惣菜管理士三級の試験範囲
2019年度10月開講分より、惣菜管理士3級のカリキュラムが変更になりました。
<以前>惣菜管理士三級の試験範囲
以前の惣菜管理士三級の試験範囲は下記の通りでした。参考程度に前回の科目も押さえておきましょう。
試験コンセプト:安全と栄養
レベル:基礎的な知識、担当者レベル
個人的に受講に当たっての感想(2015年)
該当年の試験に関して記載いたします。基本的に、「惣菜管理士問題集」のみ行えば合格可能になりました。ただし、設問の聞き方など丸暗記では対応できない工夫がしてあり、それなりに勉強することをお勧めします。周りに人は一夜漬けで合格した人もいました。僕自身は勉強しすぎたと思います。
- 勉強開始時期:試験2週間前から
- 平日の通勤時間:30分×2回
- テスト前週の土日:各1時間
- テスト前日:1時間
2018年惣菜管理士資格試験合格者および合格率
2018年惣菜管理士資格試験合格者及び合格率は、下記の通りになります。
| 級別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 一級 | 739名 | 606名 | 82.0% |
| 二級 | 1,032名 | 910名 | 88.2% |
| 三級 | 1,992名 | 1,616名 | 81.1% |
| 合計 | 3,763名 | 3,132名 | 83.2% |
「惣菜産業新聞JMニュース 2018.8.1発行」引用
ここから各単元ごとに暗記項目を記載しておきます。
「食品の特性と惣菜」で最低限覚えておきたい7つのこと
「食品の特性と惣菜」で最低限覚えておきたい7つのことは下記の通りになります。
内食、中食、外食の違いについて
内食、中食、外食の違いをは把握しておきましょう。
- 内食:家庭内で調理し、家庭やリビングなどで喫食する。
- 中食:家庭以外の場所で調理された調理済食品*を、家庭やリビングなどで喫食する。
- 外食:家庭以外の場所で調理された調理済食品を、家庭以外の特定の施設内で喫食する。
特に、中食における調理済食品を惣菜といいます。
呈味の基本(味の分類)ついて
味には、基本味の五味があります。
- 甘味
- 塩味
- 酸味
- 苦味
- うま味
呈味成分と食品例について
基本味の五味を把握したら、呈味成分を把握しておきましょう。
| 呈味 | 呈味成分 |
| 甘味 | ショ糖、ブドウ糖 など |
| 塩味 | 塩化ナトリウム、塩化マグネシウム など |
| 酸味 | 酢酸(食酢)、乳酸(ヨーグルト) など |
| 苦味 | カフェイン(コーヒー)、フムロン(ビール) など |
| うま味 | グルタミン酸、イノシン酸ナトリウム など |
| 辛味 | カプサイシン(とうがらし)、サンショオール(山椒) など |
| 渋味 | タンニン(茶)、カテキン(茶) など |
呈味成分の混合効果について
呈味成分の混合効果について記載します。
- 対比効果:2種類の異なる呈味成分を混合した時、弱い方の味が強い方の味をさらに強める現象。
- 抑制効果(相殺効果):2種類の異なる呈味成分を混合した時、一方の味がもう一方の味を弱くする現象。
- 相乗効果:同じ系統の味を混合した時、その味がより強調される現象。
| 現象 | 組み合わせ |
| 対比効果 | 甘味と塩味(しること食塩) |
| 抑制効果 (相殺効果) | 甘味と苦味(コーヒーと砂糖) |
| 相乗効果 | うま味(グルタミン酸ナトリウムとイノシン酸ナトリウム) |
甘味料と主要な甘味料の特徴について
甘味料とは、食品に甘みを付与するために使用される添加物で、砂糖の代替品として使用されます。
<主要な甘味料>
- アスパルテーム:アスパラギン酸とフェニルアラニンという2種類のアミノ酸が結合してできた物質で、甘さは砂糖の約200倍で、清涼飲料水、菓子、ダイエット食品などに使用されている。
- アセスルファムカリウム:酢酸由来のジケテンを原料として製造され、甘さは砂糖の約200倍で、生体内で利用されないため、ノンカローリー甘味料として使用されます。
- D-ソルビトール(ソルビトール、ソルビット):ブドウ糖を還元して作られ、甘さは砂糖の約0.6倍で、自然界でも植物体内に中間代謝物として広く存在している。
発酵食品と微生物による分類について
発酵食品とは、微生物の働きで保存性を高めた加工食品をいいます。発酵食品に関わる微生物は、カビ、酵母、細菌などがあります。
| 発酵食品 | 主要な微生物 |
| パン | パン酵母 |
| ビール | ビール酵母 |
| ヨーグルト | 乳酸菌 |
| 日本酒 | 麹カビ、清酒酵母 |
調味料の「さしすせそ」に関して
調味料の「さしすせそ」に関してもしっかり押させておきましょう。もともとは、調味料の使用順序として言われており、一つの考え方として一般的に認知されています。
- さ:砂糖
- し:塩
- す:酢
- せ:しょうゆ(せうゆ)
- そ:みそ
最後に
今回は、リニューアルされた惣菜管理士3級の科目「食品の特性と惣菜」で最低限知っておきたい7のことについてまとめてみました。
惣菜管理士三級を受験される方にとって、参考になれば幸いです。業務をしながらの受験になるかと思いますが、効率的に勉強しましょう。