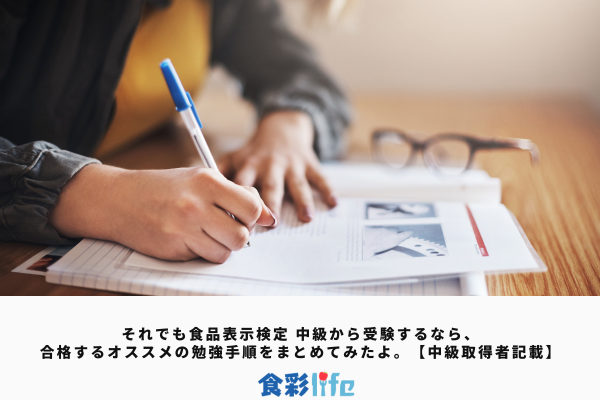どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)
前回、食品表示検定 中級から受験する4つのデメリットと2つのメリットについてまとめてみました。僕個人としては食品表示検定を初級から順番に受験することを推奨してますが、中級から受験したい方も少なからずいらっしゃると思います。
今回は、 食品表示検定の初級を受験せずに、中級から受験する時のおすすめの勉強法 について記載したいと思います。
食品表示検定 中級とは
まず、本題に入るまでに食品表示検定 中級の試験について記載したいと思います。
食品表示は、安心・安全な食品を提供する意味で重要な役割を果たしており、消費者にとって商品の品質を判断し購入する上での判断材料になります。(アレルゲン患者など)試験対象としては、食品表示を理解する必要のある生産、製造、流通の現場の人材向けになり、初級と比べて難易度が上がります。
というのも、生鮮食品、加工食品、原料原産地表記でのルールに関して、非常にややこしいのです。しかし、その知識は基礎的であり、その部分で怪しいと試験の結果も芳しくありません。初級から上級を合わせた累計合格者(第1回〜第15回まで)は41,896名に達し、食品表示検定では日本国最大の規模になっております。食品表示試験が注目されていることがわかります。
試験範囲
改訂6版・食品表示検定 認定テキスト・中級』からの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。法令は2019年10月1日時点で施行(法律の効力が発行)されているものを基準とのことです。もちろん、国内で製造・加工された加工食品の原料原産地表示の義務化に伴い、出題の対象となります。2019年1月16日に改定された認定テキストは、加工食品の原料原産地表示義務化の内容にも対応しており、食品表示のバイブルになりますよ。
合格基準と合格率
マークシート形式による選択問題で、全100問中70点以上が合格になります。
第17回 食品表示検定 中級(2018年6月13日) 合格実績になります。
| 受験者 | 3,511人 |
| 合格者 | 1,703人 |
| 合格率 | 48.5% |
| 平均点 | 68.6点 |
食品表示検定 中級の勉強法(dai流)
食品表示検定 中級の勉強法に関して下記の通りになります。
- 『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』を一読する。
- 検定対策セミナーに参加する。
- 過去問をやる。
- わからない問題は『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』で確認する。
- その全てを繰り返す。
この一連のサイクルを徹底的に行うことがかなり重要になります。通勤時間などの隙間時間を利用して、勉強しよう。
『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』を一読する
食品表示検定中級では、生鮮食品と加工食品があり範囲は広い上に、細かな知識も要求されます。そのためテキストに記載されている内容を頭に詰め込む必要があります。実際の表示例で不適切な表示部分を選択したり、与えられた条件、原材料配合から表示例を作成していく(選択式)といった高度の問題も求められますので、怪しい知識で臨むと試験を落ちる可能性がありますのでご注意をください。
【別途費用必要】検定対策セミナーについて参加する
別途費用が必要になりますが、検定対策セミナーを活用することもできます。検定対策セミナーとは、食品表示検定を運営する一般社団法人食品表示検定協会が行う、 公式の検定対策セミナー になります。食品表示検定を運営する団体による対策セミナーなので、初級受験時に検定対策セミナーが非常に良かったので、中級の時も参加しました。
もちろん費用はかかりますが、メリットもあります。2018年4月25日に参加した検定対策セミナーですが、もらった書類で「食品表示検定・中級」 対策セミナーテキスト』、第16回 食品表示検定中級問題および解答、実力診断テストおよび解答をいただくことができました。
- 参加したセミナー:食品表示検定・中級 対策セミナー
- 時期:2018年4月25日
- 持参必要なもの:筆記用具、『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』
- 講師:的早 剛由氏
- もらった書類:『「食品表示検定・中級」 対策セミナーテキスト』、第16回 食品表示検定中級問題および解答、実力診断テストおよび解答
この『「食品表示検定・中級」 対策セミナーテキスト』は、テキストを要約したものになります。(かなりボリューミーですが)前回の過去問をもらえるので、中級のみを受験する場合は必要かと思います。(仕事の同僚、先輩で前回受験しており、過去問を手に入る環境の場合は、そちらを活用してもらえばと思います。)
過去問を何度もやる。
食品表示検定の中級の試験では、全100問あります。その問題を何度も繰り返し見直すことが必要になります。もちろんそのままの問題が出題される可能性は大いに低いと思いますが、設問の出題パターン、傾向などを学ぶことができます。つまり、試験に慣れることができます。それが食品表示検定中級の試験を突破する上で、かなり重要だと思ってます。
わからない問題は『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』で確認する。
過去問を繰り返しするとわからない問題が出てくると思います。その場合、『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』の出番になります。索引からわからない箇所を調べて理解を図っておりました。それでもわからない問題はチェックしておき、全体理解が進めば理解できる場合もあるので、日にちを置いておきます。それで、後日もう一度確認して理解できるかを図ってみてください。
基本的にはそれで理解は可能ですが、できなければ諦めて暗記してください。(完璧な理解にこだわると試験範囲の広さに挫折しかねないので、ラフな気持ちで勉強することがおすすめですよ。)
その一連の流れを繰り返す
1〜4の過程で、ある程度バラバラな知識を頭の中に詰め込めたと思います。その上で、1からまた繰り返してください。それで体系的な知識の習得を目指しましょう。
独立した知識
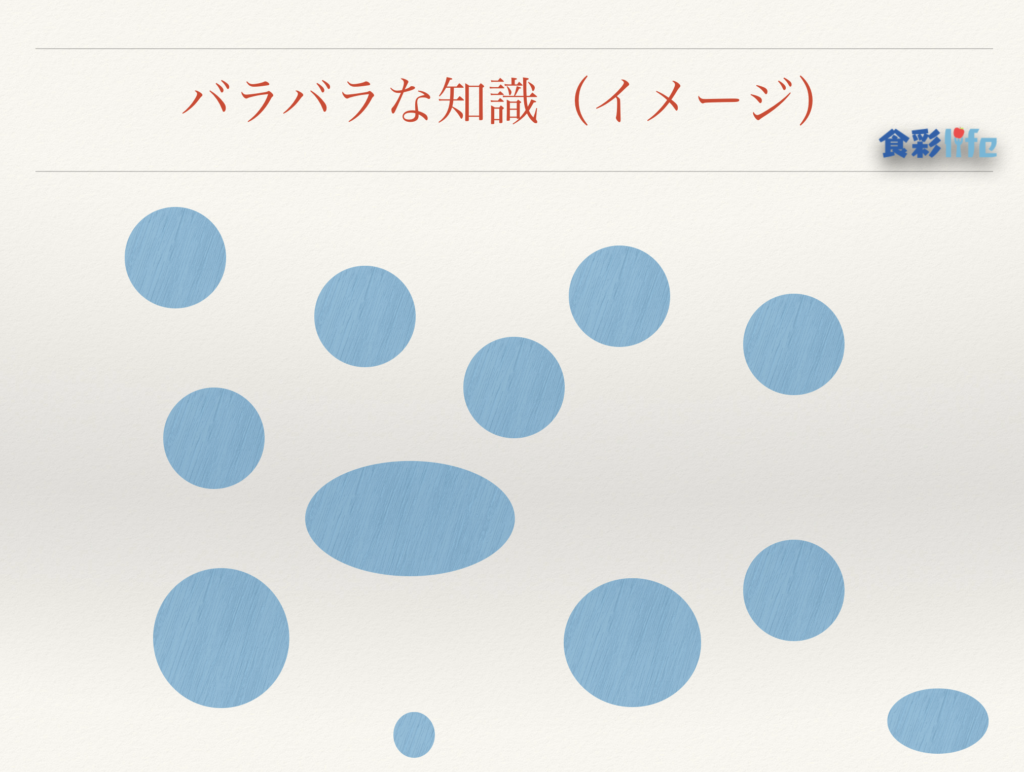
体系的な知識
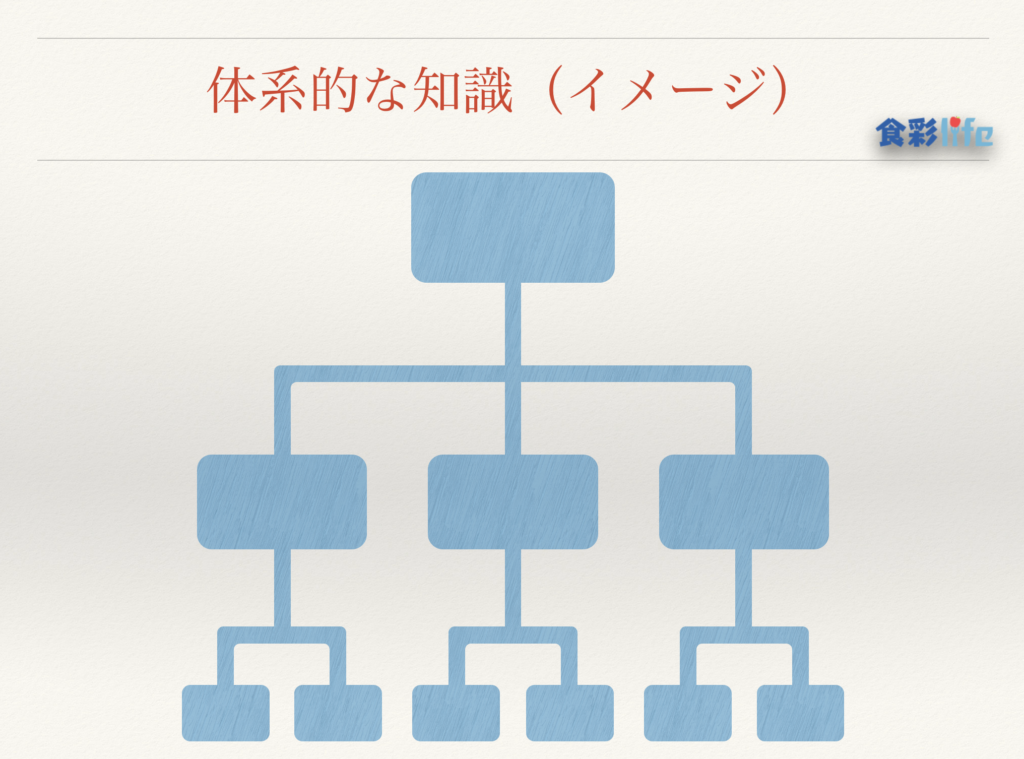
最後に
今回は、食品表示検定 中級のみを受験する場合、突破できるオススメの勉強法についてまとめてみました。
中級から受験する場合、ショートカットできますが、少し難易度が上がります。しかし、中級から受験されると決心されるのであれば、さっそく『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』を読んでしまいましょう。
あくまで僕のオススメの勉強法ですが参考になれば幸いです。勉強法は人それぞれ合う合わないありますので、ご自身の合う方法で勉強しましょう。合格さえすれば良いので^^